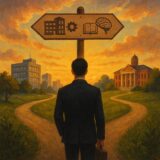最近、大学院の課題・レポートに追われる日々な毎日の中で、学校の同級生からオススメされた書籍が目からウロコだったので、紹介します。
書店にありふれた単純な”自己啓発本”って訳ではなく、人の生産力や思考法をスッキリとさせるアプローチを細かく説明されていて、非常に楽しく読破できる本だと思います。
是非、興味があれば読んでみてください。
はじめに:何を考えるか、より前に「それって考える価値あるの?」

Gerd AltmannによるPixabayからの画像
「考えてるんですけど、答えが出なくて…」
「ずっと悩んでて、どう進めたらいいかわからなくて…」
そんな風に頭を抱えたこと、ありませんか?
私自身、大学院での課題や研究テーマに向き合う中で、「ずっと考えてるのに進まない」という感覚を何度も経験してきました。
でも、それって本当に「考えていた」のか?
――そんな根本的な問いを投げかけてくれたのが、安宅和人さんの『イシューからはじめよ』でした。
読後に残ったのは、次のような強烈な自問でした。
「あなたは、本当に“考える”という行為をしていたのか?」
これまで“努力”や“学び”と信じていたものの多くが、ただの自己満足で非生産的な活動だったのでは…と気づかされ、目が覚めるような一冊でした。
「悩むこと」と「考えること」はまったく別物だった
本書の中で、最も印象的だったのはこの一節。
「悩むこと」と「考えること」は違う。
悩んでいる状態って、要は「解けない問題」に対して、堂々巡りしているだけ。
しかもその問題は、たいてい「今、自分が本当に解くべき問い(イシュー)」ではなかったりするんです。
✔ イシューとは?
本質的で、かつ、答えが出ると前に進める問い。
この定義を見た瞬間、私の思考パターンがいかに曖昧で非効率だったか、痛感しました。
ただ悩んでいるだけの時間は、生産的な思考ではない。
今まで「悩んでいる=深く考えている」と思っていた自分を、そっと脳内で反省しました。
イシューは分解できる:「Sub-Issue」の技術
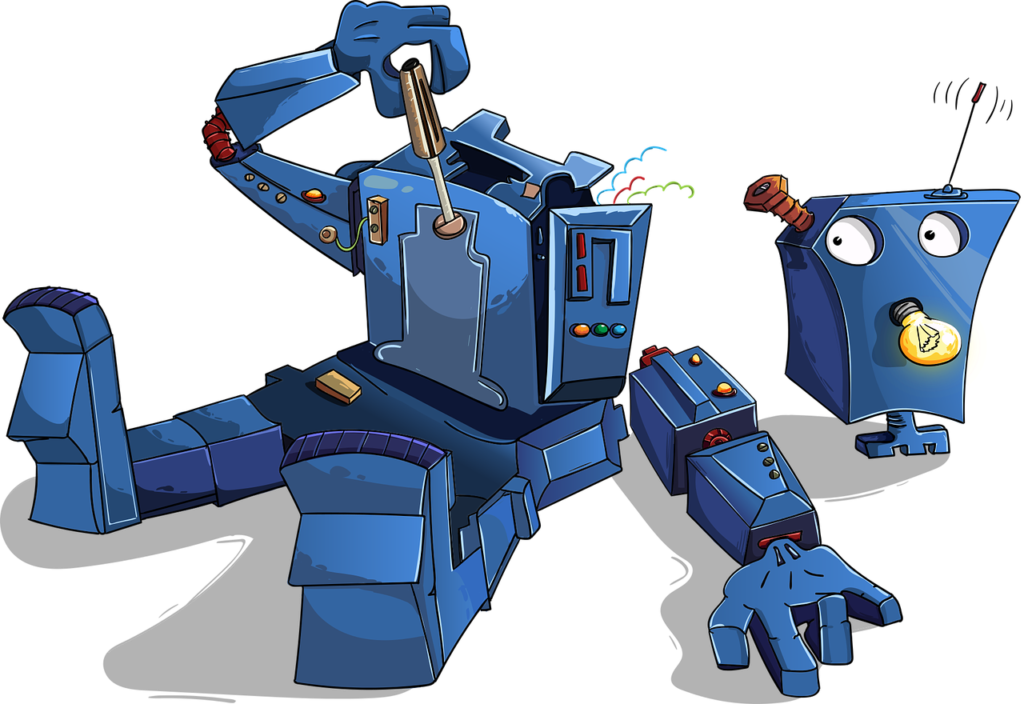
Dmitry AbramovによるPixabayからの画像
本書で得たもう一つの大きな学びが、「問いを分解する力」です。
大きな問いに立ち向かうのではなく、Sub-Issue(副次的な問い)に分解していく。
それによって、思考の霧がどんどん晴れていく感覚がありました。
✔ たとえば研究の場合…
私の研究でも「〇〇の地域定着をどう促すか?」という問いに対して、
- そもそも定着とはどういう状態か?
- なぜ離れていくのか?
- 定着の要因にはどんな変数があるか?
といった小さな問いに分けていくことで、アプローチが具体化し、一歩踏み出すことができました。
「考えても無駄な問題」は、捨てていい
この本で個人的に最もハッとした部分が、こちらの視点です。
考えても答えが出ない問題は、諦めろ。
正直、目からウロコでした。
「難しい問題にこそ、立ち向かうべき」と思っていた私にとって、この言葉は衝撃でした。
けれど、振り返れば「そもそも定義が曖昧」「判断材料が揃っていない」ような問題に、時間を吸い取られていたことってよくあるんですよね。
思考のリソースは有限。
解ける、かつ、解く価値のある問題に集中すべき。
その潔さに、感銘を受けました。
「考える」という行為にも、選択と戦略がいるのだと改めて気づかされました。
まとめ:「生産的に考える」とはどういうことか
『イシューからはじめよ』は、思考の技術書というより、知的スタンスの指南書でした。
- 自分の思考を「イシュー」からはじめる。
- 問題を分解して、解ける問いに絞る。
- 解けない問いは、勇気を持って切り捨てる。
こうしたシンプルで強い姿勢は、学習や研究、そして仕事のどの場面でも活きてきます。
「それ、本当に解くべきことですか?」
この問いを、自分にも、周囲にも投げかけ続けること。
それこそが、生産的な活動の第一歩なんだと思います。
📝この記事のまとめポイント
- 悩むこと ≠ 考えること
- イシューは「本質的かつ答えが出ると前に進む問い」
- 思考は「問いを立てる」ところから始まる
- Sub-Issueへの分解で、思考の霧が晴れる
- 解けない問題は捨ててOK。思考のコスパを大事に
 ぼちぼちPM
ぼちぼちPM 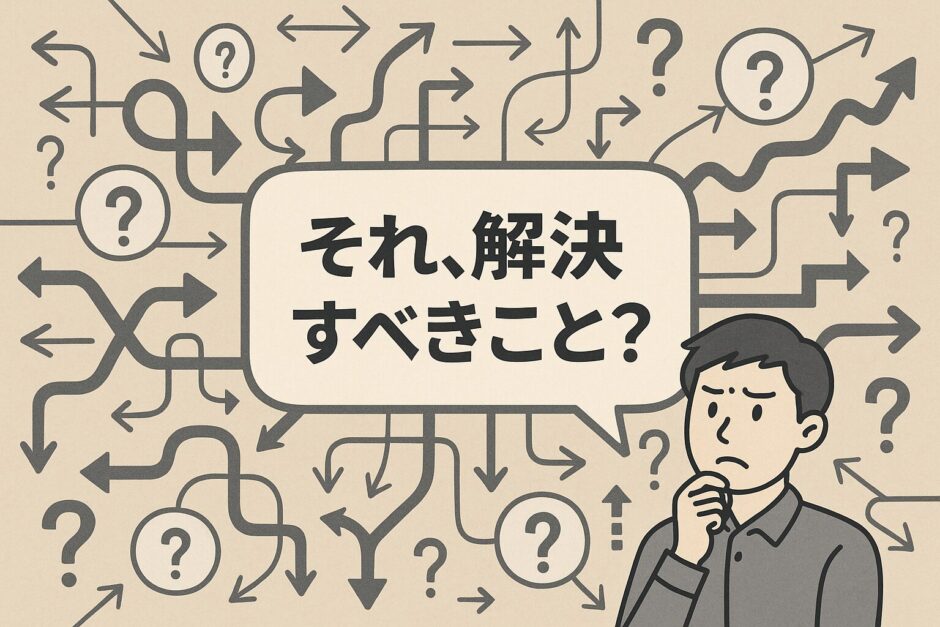

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4abd9462.98547a3e.4abd9463.7a0c845d/?me_id=1285657&item_id=12958496&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01122%2Fbk4862763561.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)